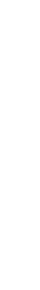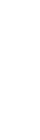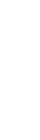COLUMN
予防接種の重要性とは? 愛犬・愛猫の健康を守るために
ペットとして家族の一員となった愛犬や愛猫の健康を守るために必要なのが予防接種です。
しかし、どんな病気から守るのか、どのタイミングで行うのか、初めてペットをお迎えした飼い主さんには分からないことが多いと思います。
この記事では、予防接種の基本的な知識から、必要なワクチンの種類、接種のスケジュール、副作用への対処法などを分かりやすくご紹介します。
あなたの大切なペットが健康に過ごせるよう、正しい知識を身につけましょう。

予防接種とは何か
ワクチンの役割
ワクチンは、病気を予防するためには欠かせません。
ワクチンを体に入れると、ペットの免疫システムはこれを「敵」として認識し、次回同じ病原体に遭遇したときに迅速に対応できるようになります。
結果として、ワクチンを受けたペットは、多くの感染症から守られます。
ワクチンを打たないとどうなるか
ワクチンを打たないと、愛犬や愛猫は病気の原因となるウイルスや細菌に感染しやすくなります。
例えば、狂犬病やフィラリアなどの重篤な病気に感染するリスクが高まります。
ワクチンによってこれらの病気を予防することは、ペットの健康を守るだけでなく、飼い主としても安心感を持つことができます。
愛犬に必要なワクチン
接種が義務付けられているワクチン
狂犬病は、感染した動物の唾液などを介して他の動物や人に感染する疾患です。
初期症状としては、発熱や無気力が見られ、進行すると興奮や攻撃的な行動が出ることもあります。
最終的には死亡に至る非常に危険な病気です。狂犬病ワクチンは、このような重篤な病気を予防するために年1回の接種が義務づけられています。
任意で受けられるワクチン
任意で受けられるワクチンとしては、パルボウイルス、犬ジステンパー、犬伝染性肝炎などがあります。
これらの疾患は、愛犬の健康を脅かすものですので、接種を検討することをおすすめします。
ワクチンで予防できる疾患
・狂犬病: 人にも感染する危険な疾患です。犬の接種は一部の自治体で義務化されています。
・パルボウイルス: 若い犬にとって致命的な下痢や嘔吐を引き起こすウイルス感染症です。
・犬ジステンパー: 高熱や鼻水、咳、さらには神経系の障害を引き起こす恐ろしい病気です。
・犬伝染性肝炎: 肝臓に影響を及ぼすウイルス感染症で、発熱や食欲不振の症状が現れます。
・レプトスピラ症: 腎臓や肝臓に障害を引き起こす感染症です。人への感染も報告されています。
・ボルデテラ感染症 (ケンネルコフ): 咳や鼻水などの上気道症状を引き起こす感染症です。
・犬コロナウイルス感染症: 主に腸に影響を及ぼし、下痢や嘔吐の症状が現れる感染症です。
子犬のワクチン接種について
子犬は、新生児期から数週間は母犬からの抗体で保護されていますが、その後は自身の免疫が成熟するまでの間、感染症のリスクが高まります。
この期間にワクチン接種を開始し、数週間おきに追加接種を受けることで、子犬期の感染症リスクを大きく減少させることができます。
愛猫に必要なワクチン
主要なワクチン一覧
・三種混合ワクチン: フィリン感染症(猫風邪)、猫カリシウイルス感染症、猫パルボウイルス感染症を予防します。
・猫白血病ワクチン: 猫白血病ウイルスによる感染を予防します。
・狂犬病ワクチン: 狂犬病を予防します。一部地域では接種が義務付けられています。
ワクチンで予防できる疾患
・フィリン感染症(猫風邪): 咳やくしゃみ、鼻水などの症状が現れる感染症です。
・猫カリシウイルス感染症: 高熱や食欲不振を引き起こす病気です。
・猫パルボウイルス感染症: 嘔吐や下痢などの消化器系の症状が特徴です。
・猫白血病: 免疫力の低下や貧血、がんなどの症状が出る病気です
子猫のワクチン接種について
子猫は、生後8週齢からワクチン接種を開始することが推奨されています。
初回接種の後、2〜4週間おきに追加接種を受けることが一般的です。1歳になったら、成猫としてのワクチン接種スケジュールに切り替え、定期的に更新することが大切です。

予防接種の副作用と対処法
副作用の種類
予防接種は愛犬・愛猫の健康を守るための大切な手段ですが、時々、接種後に不調を示すことがあります。
具体的には、体温の上昇、注射部位の赤みや腫れ、元気のなさ、食欲減退、嘔吐や下痢などの症状が一時的に現れることが考えられます。
特に、元気がない状態や食欲不振は、1~2日で改善されることが多いです。
副作用が出た場合の対処法
もし愛犬・愛猫に副作用が出た場合、軽い症状であれば家庭での対処も可能です。
発熱が見られる場合は、水分補給を促し、涼しい場所で安静にさせます。
また、元気がない時や食欲がない場合は、無理に食事をさせず、静かな環境でゆっくり休ませることが大切です。
医師に連絡するタイミング
症状が3日以上続く、呼吸の異常を感じる、ふらつきや意識の低下などの深刻な症状が現れた場合は、速やかに動物病院に連絡し獣医師の診断を受けることを強くおすすめします。
接種の副作用は一時的なものが多いですが、安心と信頼の下、専門家と連携して愛犬・愛猫の健康を守ることが最も大切です。
福岡東動物病院
気になること・不安なことがある時は、気軽に福岡市東区・香椎駅前の福岡東動物病院へご相談ください。
“動物の専門家”である獣医師・動物病院へのご相談が、不安・お悩み解消の一番の近道です。
私たちは“話をきいてくれる獣医師”“何でも気軽に相談できる動物病院”を目指して、どんなお悩みにも耳を傾けて親身に診療いたします。
“迷ったら動物病院へ相談”
それが大切なご家族の健康、そして幸せなペットライフに繋がります。
福岡東動物病院
TEL:092-663-5092
住所:〒813-0013 福岡県福岡市東区香椎駅前3丁目4-25

- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2023年12月
- 2023年10月
- 2023年6月
- 2023年3月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2020年7月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2019年9月
- 2019年6月
- 2017年12月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月